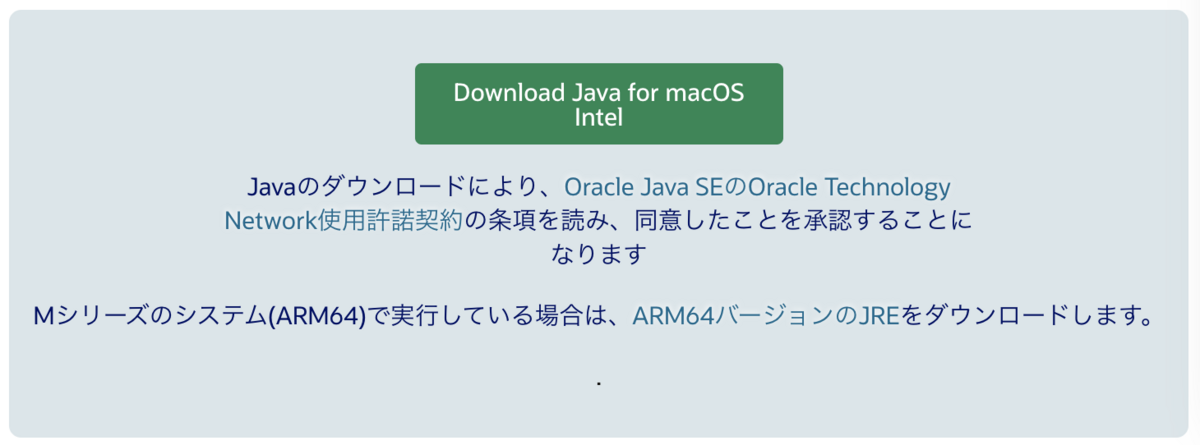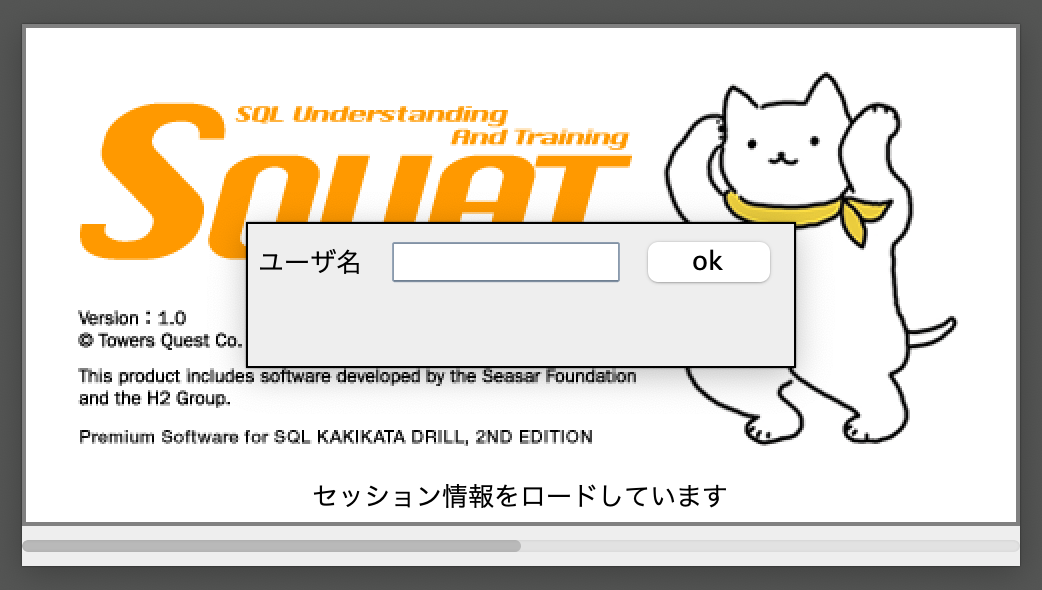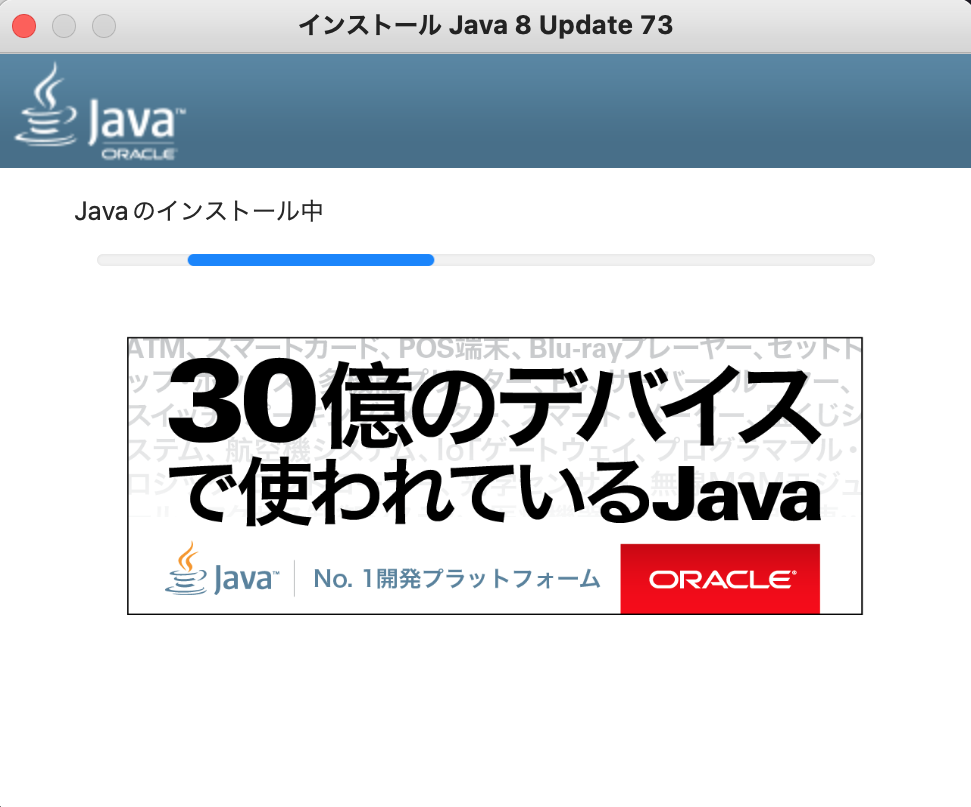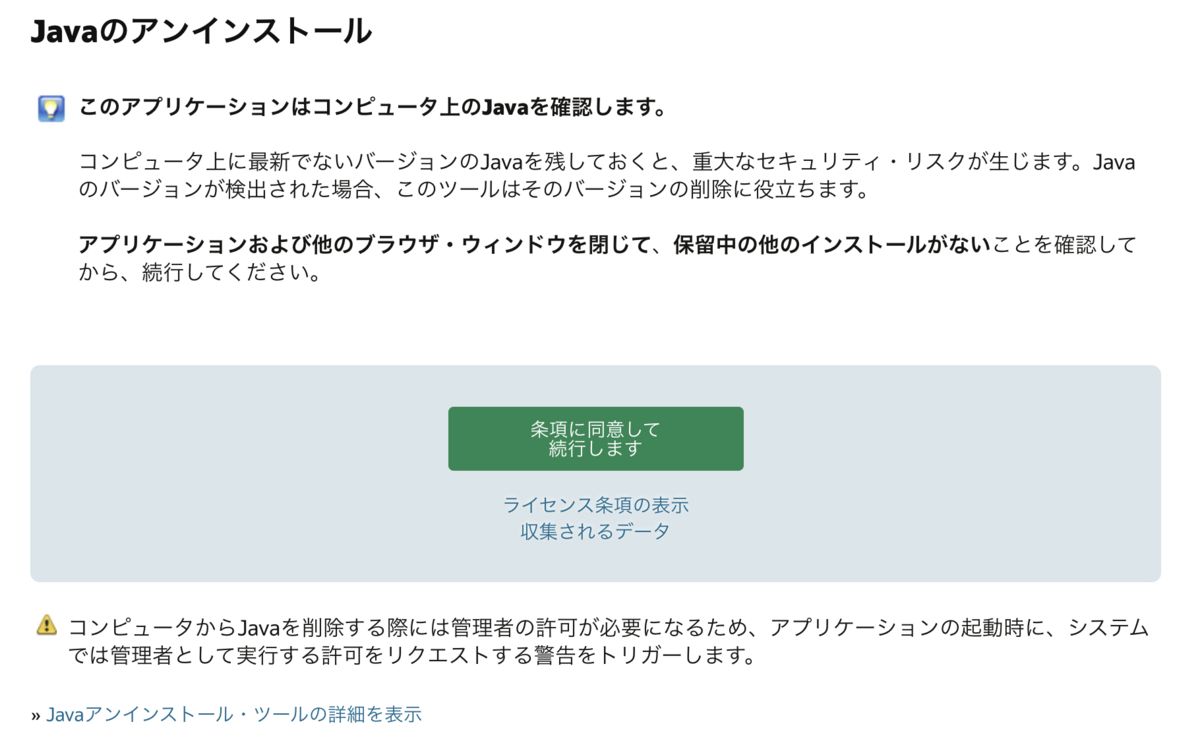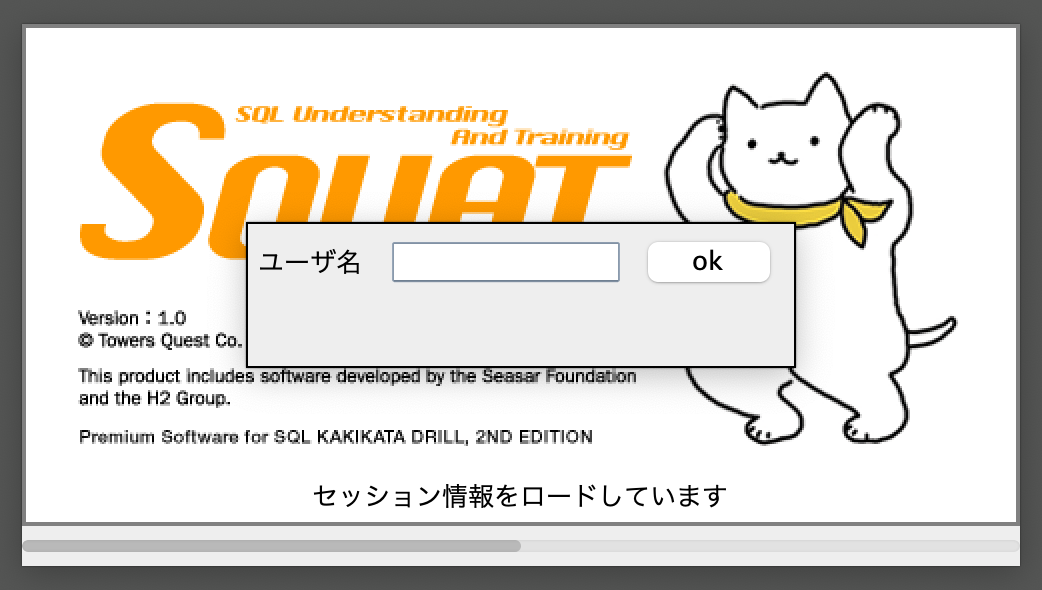2月9日から13日まで、4泊5日で広島に行ってきました。YAPC::Hiroshima 2024に参加するため。
yapcjapan.org
本編は1日だけですが、前日入りして後半2日は観光のための延泊で。延泊分を除く宿代と往復の交通費は会社に出してもらいました。そんな私の会社の自社サービスは以下。中小企業向けの請求書作成、業務管理、経営管理システムです。リーズナブルで高機能。ぜひどうぞ。
the-board.jp
最初にYAPCに参加した2013年、今の会社にはまだ入ってなくて、IT業界には縁もゆかりもないフリーランスの編集者でした。当時の記録は以下。一生懸命書いてます。
note103.hatenablog.com
直近数回の記録も並べときますね。2018の沖縄ではスピーカー、2019の東京ではLTをやりました。我ながらすごいね。
- YAPC::Okinawa 2018 の思い出 - the code to rock
- YAPC::Tokyo 2019 に参加しました - the code to rock
- YAPC::Japan::Online 2022に参加した - the code to rock
- あれから10年の現在地〜YAPC::Kyoto 2023に行ってきた #yapcjapan - the code to rock
今回はとほほさんが来るというので、これはマストだろ・・ということで昨年11月にチケットをゲット。広島、高校の修学旅行で行って以来だし。原爆ドームには行ったはずだけど、「空が広かった」以外まじで何も覚えていない。もう50歳目前だし、ひょっとしたら人生最後の広島になるかも、みたいなこともあってチケット買うところまではあんまり悩まなかったんだけど、年末あたりから「あれ、もしかしてもうすぐでは・・?思ってたよりすぐかも?いや〜〜、面倒だな!!」みたいになり始め、とにかくリモートワークにどっぷりで外に出るのも億劫になっていたし、以前新幹線に乗るときにApple Watchで改札を通過できず、そのリカバリーで時間ぎりぎりになったトラウマなどもあったので、それが再現されるのではとつらい心境に。
しかしまあ、とほほさんを間近で見られるのだから、と自分を鼓舞して、なんとか新幹線にも間に合って(改札は拍子抜けするほどすんなり通過)、いざ広島。乗ってしまえば快適な新幹線。富士山もうんざりするほどデカい。
広島駅に到着、とりあえず一度は乗ってみたかった路面電車に乗って(たぶん人生初)、宿に向かう。

その後、ひと息ついて前夜祭へ。

前夜祭
会場に着くと知っている人が何人か。見かけるたびに声をかけて挨拶。いつも会う人ばかりというわけでもなくて、あれ、こんなところで!みたいな人もけっこういる。その意外性が楽しい。
前夜祭では前に椅子席、後ろに飲食あれこれ。めっちゃ喉が渇いた状態で到着してしまったので、まさかこのままトーク系がすべて終わるまで飲まず食わず・・?と思ったら、トークの前にとりあえず乾杯するから、まずは何でも飲み物を取って、とのアナウンス。その後の食事も適当なタイミングで促されて、今回のYAPCはほんとに徹頭徹尾ホスピタリティが素晴らしかった。
トークではキャッシュバスターズの話がよかった。もうその頃には会場後方の歓談がけっこう盛り上がっていて、後ろの方に座っていた分ちょっと聞き取りづらかったけど、それもまたYAPC。しっかり聞きたいなら前に行けばいいし、食事やおしゃべりを楽しみたかったら後ろに行けばいいし、どっちも混在しているのがどこか心地よかった。
1分間の超ミニLTみたいな番宣コーナーもTiktok時代のLTぽくてサクサク感が良かった。久しぶりに見る人、初めて見る人、いろいろいる。翌日以降の簡単な予習みたいになっていた。
ケータリングはどれも美味しくて、とくに小さいプラスチックの容器に入ったオードブルみたいなものがどれも気が利いていてよかった。地味だけどシメジと貝柱のローストみたいなもの、あとポテサラがむちゃ美味かった。後からコバケンさんにどんな業者(店)に頼んだのかと聞いたら、会場と同じ施設の1階に入っている店で作っているという話だった。
終了後、会場で会った久しぶりの人やその知り合い(つまり初対面)の人などと軽飲み。近くにあった野菜中心のなんか洒落た飲み屋。しかし終わってみれば一人2,200円。安!
本編
charsbarさん
前日、前夜祭の時点ですでにけっこう飲んでいて、その後さらに飲んだのでなかなかの二日酔い。大体カンファレンスのときって初日に飲みすぎる。というかとくに酒も強くないし。加えて朝は弱いので、オープニングは無理せずスキップしてゆったり会場入り。目指すはcharsbarさんの「2024年冬のPerl」。
fortee.jp
ええ、Perlってもう5.40になるの・・!という驚き。ぼくが最初にPerl入学式で触った頃はたしか5.18とか。その他にもいろいろ話題はあったけど、各種の新しい機能紹介とcharsbarさんによるその機能への評価(というか距離感というか)が何とも面白い。コミッターを育てるためにあえて力のある人が開発のメインに回らず、メンターになるなどの話もなるほど感。
ちなみに、遅れて入ったので最初はよくわからなかったんだけど、charsbarさんはリモート参加だった。昨年の京都以来で久しぶりに会えるーと思っていたけど会えなかった。と、たしか質疑応答でskajiさんも言っていた。
三谷さん
次に見たのは三谷さん(@shohei1913)の「VISAカードの裏側と “手が掛かる” 決済システムの育て方」。
以前にbuildersconでKyashの人が発表した内容に近いかな・・と思って見ていたら実際けっこう近かった。その重なるところと異なるところの差分が面白かった。
Kyashの人の発表はこれ。
blog.kyash.co
動画もある。
www.youtube.com
三谷さんのは20分という時間もちょうど良かった。ぎゅっと圧縮された濃密な内容がサクッと終わる。結果的にベストトークに選ばれていたし、自分的にもこの時点ではベストトークでした。
やんまーさん
一日を通しての心のベストテン第1位はこれ。「awkでつくってわかる、Webアプリケーション」。
fortee.jp
speakerdeck.com
結論としては「awkでつくるな」なんだけど、硬軟取り混ぜた内容でこれもあっという間の20分。
声が通った発表でスライドも見やすく、質疑応答も活発。ベストトークに投票しました。
アナグラさん
しばらく休憩ののち、さっきと同じ会場でアナグラさんの「rakulangで実装する! RubyVM」。
fortee.jp
speakerdeck.com
アナグラさんはcodehexさんと並んでYAPC沖縄で本当にお世話になった。以前は若い学生さんという雰囲気だったけど、もう大学講師のような落ち着いた語り口。弾さんがちょいちょい口を挟んでくれるのも楽しい。
三谷さんからここまでの3本はどれも似たような軽快さがあった。本当はあんまりがっつりトークをハシゴするのももったいないというか、いずれ動画でも見られるものにわざわざ張り付かんでも・・と思っていたけど、この3本はタイトルだけでも面白そうで外せなかったし、見れて良かった。
ランチセッション
お昼は外もありかと思ったけど、外に出る機会は翌日以降にいくらでもあるし、弁当は人数分用意してあるというのでランチセッションへ。Helpfeelとnoteのトークセッション。
前半はスライドの出力が安定せず大変そうだったけど、最後まで進行しきって内容的にもあまり語られない(ある意味センシティブな)ところにザクザク踏み込んでる感じでよかった。
この内容については以下で公式に記事化されていた。
engineerteam.note.jp
当日の音声もHelpfeelのポッドキャスト「今出川FM」で公開されているようで、そのうちその場で話しきれなかったスピンオフ(アフタートーク)も公開されるらしいです。
blog.notainc.com
スポンサーブース
前回の京都では数えるほどだったスポンサーのブースが一気に増えてスタンプラリーも開催されていました。
blog.yapcjapan.org
ぼくは全然回りきれなかったけど、とりあえずFastly、Helpfeel、SmartHR、ライザップは回りました。このうち、FastlyではオリジナルのかっこいいUSBケーブルが当たり。これは嬉しい。旅行に最適。

その他、この部屋ではもみじ饅頭などの広島銘菓、朝食として配っていたおにぎり、はてながスポンサードしていたオリジナルコーヒーなどの飲食物が充実していて、いろいろいただきました。生もみじとコーヒーの相性は半端なかった!

ノベルティ
今回も力の入ったノベルティが多かった。各社の皆さん、ありがとうございます。中でもカヤックさんの「ステッカー御朱印帳」はまさに顧客が求めていたものという感じで快哉を叫びました。ほんとにこれが欲しかった(笑)。お金出すのであと5冊ほしい。
詳しくはこちらをどうぞ。
techblog.kayac.com
その他だとLayerXさんのストレッチバンド。
tech.layerx.co.jp
この記事内にあるCTO松本さんの動画、ひと目でわかる大胸筋の厚みにトレーニングへの本気を感じる。ちなみにぼくも一応ジムは通っていて、ちょうどこういうストレッチバンドが欲しかった。
筋トレとエンジニアといえば、昨年10月に浅草で開催された大江戸Ruby会議10でのbash0C7さんによるこの発表。未見のエンジニア・トレーニーにはぜひ見ていただきたい。
speakerdeck.com
休憩
朝からここまでノンストップで会場に詰めていたので、一旦抜け出し、ノベルティなど重くなった荷物をすべて宿に持ち帰る。しばらくボケーっと休憩して、身軽になってまた会場へ。
この間にtwadaさんやそんむーさん、弾さんなど目をつけていたトークが軒並み過ぎ去ってしまったけど、自分のペースを取り戻せたのはよかった。とにかく朝イチの二日酔いがきつかった。
まこぴーさん
会場に戻って、まこぴーさんの「PerlでつくるフルスクラッチWebAuthn/パスキー認証」を途中から。
fortee.jp
speakerdeck.com
途中からだからわからないのか、最初から見てもわからないのかはわからないけど、ひたすら繰り出されるデモはとにかくなんだか凄そうで、集中して見ているうちに終わってしまった。パスキー設定、ユーザーとしてようやく使い始めたところだったので、あらためて動画もチェックしたい。
まこぴーさんは前日の1分LTのときにキラキラシールを配っていると言っていたけど、もらいそびれてしまったのが心残りだった。
トークセッション
そのまま大ホールに残って、トークセッションの「平成のエンジニアから令和のエンジニアへの遺言〜技術情報を伝達する手段の変遷〜」。
概要としてはこちら。
blog.yapcjapan.org
企画・登壇の941さんによる振り返りはこちら。
blog.kushii.net
登壇者から見た現在の若者観とか、ぼっちになったらどうする、とか刺さるテーマが沢山。twadaさんが喋っているのは多分初めて見たけど、じっくり考えながらコレという話を狂いなく突き刺して提示してくるそのクオリティがさすがtwadaさんという感じだった。
直也さんはなんといっても声の聞きやすさ。安心感と安定感。何を話しても何一つこぼさずこちらに届けてくるところにtwadaさんとはまた違った意味での経験の厚さを感じさせる。
ぼっちの件。「発表すればいいんだよ」的な結論だった気もするけど、それなりに発表を繰り返してきた自分としては「発表してもぼっちだよ!」とは言いたい(笑)。むしろデフォルトぼっちでしょう。直也さんが「誰でも最初はぼっち」と言っていて、直也さんですらそうなんだ〜と感嘆しつつ、しかし「最初だけじゃないよ!」とも言いたくなる。
はあ、とにかく初めて参加した2013年のYAPC::Asia の懇親会と言ったら。額に入れて飾りたいぐらい悲惨な懇親会だった。おそらく過去最凶につらかった。知り合いがまったくいないわけではなく、見れば挨拶できる人もいるけど、それだけ。会話にはならない。そのまま2時間ぐらい?食事と酒だけが進む感じ。なぜここにいるのか?と湧き上がるように何度も思う、あの感じ。まじで後悔と帰るかどうするかという逡巡がないまぜになったまま会場を何周もウロついた。本当に、何周も。
あのー、そんなんだったら無理せず帰ればいいんじゃない?という感じだけど、そうじゃないんだなあ。ぼっちでも残った方がいいんだよ。知らないものをじっくり観察する、それに触れることに意味がある。知らない空間に身を置くだけで得られるものがある。居心地は良くないよ。だけど、それが嫌だからって帰っちゃったら、また昨日までと同じ日常を繰り返すだけじゃん。それが嫌で飛び出してきたわけで。飛び出せ、飛び出せ。そんな歌もあります。
居心地の良いところにずっといちゃ駄目だ。そんなことしたら、居心地の良い場所がどんどん小さくなっていく。飛び出せ、飛び出せ。何かやったら、好きなものも嫌なものも手に入る。車が走れば排気ガスは出るよ。良いことも悪いことも一緒に受け入れるしかない。ぼっちは避けるようなものじゃないよ。全身で浴びながら進むんだよ。そう思わん?
・・ってまあ、実際はそれをやってるうちに、喋れる相手が増えてくるんだけど。
キーノート
何よりこのために来ました、というとほほさんのキーノート。すんごく物腰の柔らかい、威圧感が皆無で、自分をけっして大きく見せようとしないその佇まいに衝撃を受けた。本当にすごい人ってこうなんだよなあ!という感じだった。当たり前のことのように話す一つひとつの話題が、いやいや、それ全然普通じゃないですから(笑)と突っ込みたくなる感じ。
全部終わって、懇親会の撤収をする頃にようやく声をかけることができて少しお話ししたんだけど、そのときの「うん、うん」とすごく親身に話しを聞いてくれる感じ、こういうコミュニケーション、昔あったなあ〜、と懐かしい気持ちになった。人と人との関係にメリットもデメリットも介在しない感じ。ただ目の前に人がいて、その人の話を正面から聞くだけというコミュニケーション。この人は自分の役に立つのか、立たないのかなんて一切関係ない感じ。
とほほさんのすごさを分析はできない。ただ参考にするだけ。こんなふうになんか好きなことを一生懸命やってみよう、と思った。
発表で印象に残ったことはありすぎだけど、ひとつ挙げるなら、とほほさんが自分のサイトで目指しているのは「初心者向けの入門記事」と「熟練者向けのリファレンス」を兼ねる内容にしたいということ、そして「それがなかなか難しい」ということ。
懇親会
先述の地獄の懇親会から10年余り。果たして今回はどうだったかというと、そこそこいろんな人と喋れた。そのうち知らない人は3割、既知の人が7割ぐらい。それでも、会場全体の7〜8割ぐらいは知らない人。10年経ってもこれなんだから、初めのうちはぼっちだなんて当たり前すぎる。
こういう懇親会では飲み食いに一生懸命になるタチで、食事をゆっくり取れるようにとりあえず空いてるテーブルの一角をキープして黙々と食べる、みたいなことが多い。今回もそんなふうにしていたら近くにいた人(知らない人)がけっこう話しかけてくれた。以前はどうだったろう?そんなこと、あんまりなかった気がするな。一体何が違うんだろう。年齢?佇まい?よくわからないが、黙々と食べてるだけなのに話しかけてもらえるなんて、ありがたい。
知ってる人も話しかけてくれる。どこにいたの?と思うところから不意に現れる。嬉しい。しばらく話をする。考えてみると、最近ではもうTwitterとかでも一方的に眺めているだけで、メンションでやり取りとかほとんどしない。ぼくはもうTwitterではパレスチナとかフェミニズムとかLGBTQとか、そういう社会問題ばかり追いかけているし。知り合いとやり取りをするような共通の話題もほとんど投稿していない。だからこういう場でフラットに話せるのがありがたい。
こちらからは数人だけ、知ってる人に話しかけた。しかし会場は知らない人だらけだから、その知ってる人もなかなか見つからない。このときにとほほさんも探したけど(かなり真剣に)、見つからないので「懇親会はパスされたのかな」と思っていた(実際は違った)。なので単に人を見つけるのが下手なだけかもしれない。
全部終わって、上着を着て、最後にとほほさんとも話ができてよかった〜なんて思いながら会場を出る途中でThe Perl Foundationの野崎さんに遭遇して、少しだけ話せた。野崎さんもすごい人なのにぜんぜん威張らない。広い世界を知っている。LTを見てそんな感じがしていたからリラックスして話せた。
会場を出てから、ああそういえば、結局twadaさんとは話せなかったなと気がついた。懇親会で何度か見かけたんだけど、あとで話しかけてみよう、と思っているうちに終わってしまった。もしかしたらライブの出待ちみたいに、出口近くにいたら会えるかなと思ってぼんやりあたりを見回していたら、本当にtwadaさんが出てきたので話しかけた。トークセッションが面白かったこと、自分は以前からそこそこ人前で発表しているけど、壇上では本当に言いたいことをどうしても言い切れないと感じていること、和田さんのあの壇上での落ち着きと的確さはどういうところから生まれるのかみたいな話。
和田さんはこれもまたトークセッションのときのようにじわじわと考えながら答えてくれて、それは控えめだが大胆で、やはりシンプルなものだった。そのまま踏襲することはできないだろうけど、できるかぎり自分に反映させたい。
雑感〜日本人率と男性率
話を閉じる前に、ここまでに入らなかったトピックを2つほど。
YAPCと同様に全国行脚スタイルで毎年開催しているカンファレンスにRubyKaigiがあるけど、それに比べて外国人がほとんど参加していないのが特徴的だなあ、と思った。これは必ずしも悪いことではないかもしれないが、これだけの人数が参加しながらどちらを向いても日本人ばかりというのはやはりこのイベントの特徴だと思える。去年の京都でも、自分が英語で喋った相手はフィンランドから来ていたウクライナ人のアンドリーさんぐらい。
べつに海外から来るとかでなくても、日本で働く外国人は少なくないはずで、そういう人はどうしているのかとちょっと思った。もし日本語ネイティブじゃない人が来るなら、スライドも基本英語で作る必要があるだろう。喋りは日本語OKでも、スライドは英語マスト。たしかVimConfはそんな感じだったような。
もうひとつ、これは一種の課題として捉えられると思うけど、圧倒的な男性率。男、多いな〜!と思った。前夜祭では後ろの方に座っていたんだけど、前に座っている人たちの後頭部がことごとく男性。RubyKaigiですらまだ男性の方が多いと思うけど、それでもYAPCと比べたら遥かに女性が多い。この違いって何なんだろう?
まあ、YAPCの男性率が高いというより、RubyKaigiの女性率(というかジェンダーレス度合い)が他より図抜けて高いということなのかもしれないけど。
以前、RubyKaigiに参加した女性がその感想を述べる中で、参加するとどんな良いことがあるかという話のひとつに「トイレが空いてる」というのを挙げていた。ITカンファレンスでは通常のイベントに比べて女性率が低いから、トイレに並ぶ時間も少なくて済むということ。その発想はなかった。そしてもちろん、それは参加する女性にとっては良いことに違いないが、必ずしも喜ばしい話ではないだろう。もっと女性が(あるいはいわゆる男性に収まらない生き方をしている人が)参加しやすくなった方がいい。トイレの行列はもちろん、並行して解決されなければならないけれど。
終わりに
本編の懇親会の後はもう二次会とかには行かず、おとなしく帰って早めに寝た。翌日には、とほほさんに教えてもらったお好み焼き屋に朝から行かなければいけなかったし、平和記念資料館や原爆ドームにも行かなければいけない。YAPCの本番は終わったが、広島の本番はようやく折り返し地点。ここから先の話は、そのうち雑記ブログの方に書きます。
最初にも書いたけど、広島、ほんとに来るのがつらかった。とくに出発の1週間前ぐらい、ひたすら「このまま家でぬくぬく眠っていたい!」と思っていた。なぜわざわざこの寒い中、新幹線で往復8時間もかけて見ず知らずの土地に行かなきゃいけないのか?と自分を呪った。でも来て良かった。延泊時の体験も半端なかった。人生が変わるレベル。YAPCがなかったら来なかった。
スタッフの皆さん、登壇者やスポンサーの皆さん、ありがとうございました。参加者の皆さん、おつかれさまでした。会えて良かった。現場にいたのに会えなかった知人、何人かいました。でも生きてればきっと。またどこかで会いましょう。